「きょどる」という言葉について耳にしたことはありますか?
最近ではあまり耳にしなくなったため、もう「死語」とも言われることもあるようです。
ですが、その意味や由来、使い方には意外と興味深いものがありますよ!
主に若者言葉として使われてきた「きょどる」という言葉について、その意味や語源、由来を詳しく解説しながら、「きょどる」がすでに死語になってしまっているのか、考察していきます。
最後に、「きょどる」の使用シーンを面白いストーリー形式で紹介していきますので、死語と言えるかどうか一緒に考えてみてくださいね。
「きょどる」とは?

まずは「きょどる」の意味や語源を確認していきましょう!
「きょどる」の意味
「きょどる」とは、人が通常の振る舞いとは異なり、落ち着かない様子や普段とは異なる奇妙な行動を取ってしまうことを指します。
特に緊張やプレッシャーの多い状況に追い込まれたときに見られる症状です。
例えば、次のような行動が「きょどる」状態と言えます。
- 面接中に質問された際、緊張のあまり答えがすぐに出ないため、不自然に笑ったり、頻繁に顔や首を触るなどしてしまう。
- 新しいクラスや職場で自己紹介を求められた時、声が震えたり、言葉が詰まったりして、思うように話せない状態。
- パーティーや集まりで注目されると、焦って飲み物をこぼす、または話している途中で話題が飛んでしまうなど、普段と異なる振る舞いをしてしまう。
このようにして、緊張やプレッシャー、不安が知らず知らずのうちに具体的な行動として表れてしまうことを「きょどる」と言います。
「きょどる」の語源
「きょどる」という言葉の語源は、一般的には「挙動不審(きょどうふしん)」を表す言葉として使われるようになったと考えられています。
「きょどうふしん」を砕けたニュアンスで親しみやすく、そして短くキャッチ―で言いやすく短縮した形が「きょどる」ですね。
「挙動不審」とは、普通ではない、あるいは不自然な動きや行動を示すことを指します。
「挙動不審」は、人が緊張、不安、恐怖、あるいは何らかの精神的な圧力を感じている時に、普段とは異なる、不安定やおかしな行動をとる様子を表現するのに使われます。
たとえば、人目が気になり視線が定まらない、手が震える、必要以上に周りを見回す、話す際に言葉が詰まるなどが挙動不審の具体的な例です。
でも、「○○は挙動不審だよね」というよりも「○○はきょどってるよね」の方が何となく親しみやすさを感じませんか?
「きょどる」は死語?
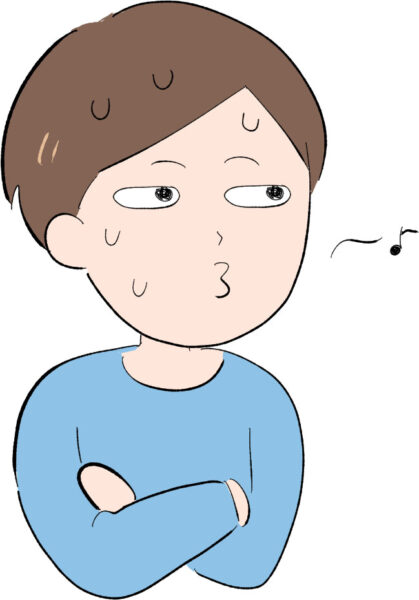
さて、「きょどる」という言葉は聞いたことがあるけれど、最近はあまり聞かないな、という感覚もあるかも知れません。
実は「きょどる」はすでに死語なんじゃないか、という話もあるくらいです。
「きょどる」は本当に死語なのでしょうか?
よくよく調べて見ると、「きょどる」は意外と新しくない言葉ではありますが、”死語”というほど使われなくなった言葉ではない、と言えそうです。
ここでは、「きょどる」が使われ始めた時期や、この言葉を使う年齢層から考察してみましょう。
「きょどる」はいつから誰が使い始めた?
「きょどる」という言葉は、2000年代初頭に若者言葉として登場したようです。
この言葉の広まりにはインターネットの役割が大きく、特に若者たちがオンラインでのコミュニケーションを通じて新しい言葉を創造し、共有する文化が発展していた時期と言われています。
掲示板などのプラットフォームで誰かが「挙動不審」の状態を「きょどる」と言い始めたのが発端ではないかと考えられています。
具体的に誰が使い始めたのか、というところまでは特定できるものではありませんが、インターネットの影響はやはり大きかったと思われます。
緊張や不安からくる特有の行動を指す「挙動不審」を表現する便利な言葉として、特に学生や若い世代の間で頻繁に用いられるようになり、「きょどる」は全国的に知られるようになりました。
「きょどる」を使う年齢層
「きょどる」を使う年代について考察すると、現在では主に20代後半から30代の人々が若い頃に親しんでいた言葉のように思えます。
確かに40代以上の人が「きょどる」という言葉を使っているイメージはあまり思い浮かばないのではないでしょうか?
しかし、時代が進むにつれて、新しい若者言葉が登場し、「きょどる」という言葉の使用頻度は自然と減少していくものです。
それでも、この言葉が完全に消失したわけではなく、特定のシチュエーションでその便利さと表現力から引き続き使われています。
ですから、”死語”というにはまだ早いと言えそうです。
「きょどる」の使われ方をストーリーで紹介!

では、「きょどる」が死語となっていない、というのを実感していただくため、「きょどる」を使ったいくつかの面白ストーリーを用意してみました。
ストーリーにすることで「きょどる」「きょどって」いる様子がそのシーンと共にすっと自然と入ってくると思いますので、楽しんで読んでみてくださいね!
初めてのプレゼンテーションで「きょどって」しまう
大学生のAさんは、授業の一環で行われるプレゼンテーションが初めての経験でした。
準備は万端に整えていたものの、本番の舞台に立つと、突如として緊張が襲い掛かりました。
足はもじもじと不自然に動き、手に持ったノートからは視線が外れず、声はまるで冬の風のように震えていました。
スライドを進める手も震え、時折言葉を詰まらせながらのプレゼンテーションとなり、聴衆の前で完全に「きょどって」しまったのです。
緊張のあまり「きょどって」名前を呼び間違える
新社会人のBさんは、入社して初めての部署の飲み会に緊張の中参加していました。
特に尊敬する上司である佐藤さんに話しかける機会を伺っていたBさんは、その瞬間を迎えたとき、緊張のあまり彼の名前を「鈴木さん」と間違えて呼んでしまいます。
実際には佐藤さんも鈴木さんも部署内の上司で名前が似ているため、誤って鈴木さんと呼んでしまったのです。
このミスに気づいた瞬間、Bさんの顔は真っ赤になり、その場で焦りと恥ずかしさで言葉が詰まってしまいました。周囲の目が一斉にこちらに集まる中、Bさんは必死に何か言おうと口を開けるものの、うまく言葉が出てこない。
「えっと…あの、すみません、佐藤さんですよね…」とようやく訂正を口にしたものの、その間も足はもじもじと動いており、明らかに「きょどって」いる様子が誰の目にも明らかでした。
気になる子を前に「きょどる」姿を露呈
Cさんは普段、どんな場面でも冷静沈着で知られていますが、友人のパーティーで意中の女の子を見つけてしまった瞬間、その落ち着きは影を潜めました。
彼女が他の人と話しているのを見て、Cさんは近づきたいと思いつつも、どのタイミングで声をかければいいのか決めかねていました。
パーティーの中で彼女がちょうど一人になった瞬間を見計らって接近しようとしたものの、足元はふわふわと不安定で、一歩進むごとに不自然に体重をかけ替えてしまいます。
Cさんは何度か彼女のいる方向に歩を進めたものの、途中で他の知り合いに見つかり、話しかけられると完全に動揺し、その場で足を止めてしまいます。
視線も落ち着かず、彼女をちらりと見ることしかできず、目が合いそうになるたびに急に視線をそらしてしまいます。
あまりにも動きがおかしいので、Cさんが普段見せない「きょどる」姿にみんなに気づかれてしまいました。
「きょどる」は死語?のまとめ

「きょどる」という言葉は、これは2000年代初頭に若者たちの間でブームになったスラングで、緊張や不安で足がもじもじ、声が震えちゃうような状態を指す、ということが分かりましたね。
元々は「挙動不審」をもっとカジュアルに言いやすくしたものなんです。
一時期「もう死語?」とも言われてましたが、意外と生命力があって、今でも20代後半から30代の人たちには割とポピュラー。
ネットが普及して、さっと新しい言葉が広がるこの時代に、ちょっと緊張したりした時に「きょどってる」という表現はまだまだ現役で活躍中です。
最後のストーリーで紹介したように、「きょどる」を特定の場面で使うとすごく便利で、会話がグッと身近になるような気がしませんか?


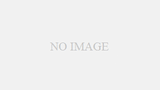
コメント